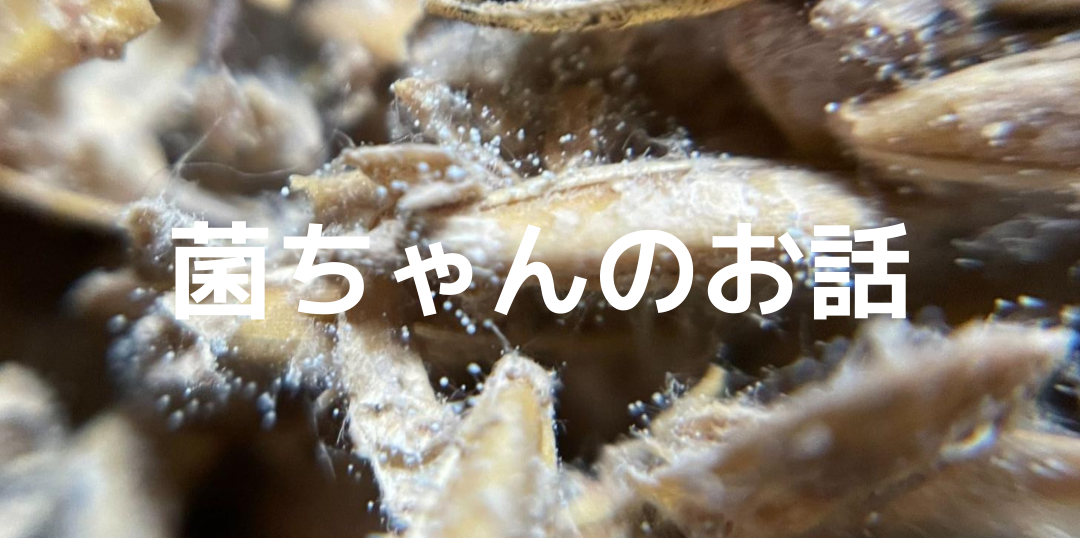微生物のこと。知れば知るほど楽しくなってきました。
それと同時に自分は現代農業について知識がなくて本当によかったと感じます。
一昨日、もみ殻発酵菌の研究をしている方とお話してきました。
もみ殻に有用微生物群を増やして畑にいれるのです。
そうすると植物さんと微生物で見事な共生関係ができます。
写真にあるのは有用菌を顕微鏡で見たものです。
納豆のねばねばみたいなものを菌糸といいます。
菌と菌はこの菌糸を武器として自分たちの縄張りを広げていきます。
とにかくこのもみ殻発酵菌は、畑の強力な助っ人外人となりそうな予感。
そんなもみ殻を使っている農家さんのところへ案内されました。
木材チップともみ殻発酵菌で成功した農家さんはさらに収穫量を
増やそうと堆肥をつくりはじめました。
この堆肥をつくるために、食品工場の残り物、茶殻、更に鶏ふんまで
使って堆肥をつくり始めたようです。
でもそこからムシがでるようになって…トウモロコシなどはほぼ壊滅状態でした。
畑にとって、微生物にとって、野菜にとって何が有効で、何が良くないのか!?
検証せず何でもやってみてしまっているのが…もったいない気がしました。
具体的に畑にいれるものとしては、
落ち葉→◎、木材チップ→◎、もみ殻→◎、茶から→△、
食品工場の残り物→☓、鶏ふん→☓、油かす→☓…
こんなイメージでした。農業素人だからわかるのかも知れません。
それくらい色んな畑をみているので共通項が自然と見えてきます。
生産者さんは未だに虫喰いの原因がわからなくてお困りでした。
疎まれること、覚悟でメールしなくてはなりません。
有機農業の大先輩に意見するのですから…。
畑の中で発酵環境をつくれば堆肥なんて作らなくとも立派な野菜ができること。
恐らく信じてもらえないとおもいますが、ダメ元でお手紙送ってみます。
結果については次回ご報告させていただきます。
農業の世界にはびっくりするほど、固定概念が存在します。
●肥料がなければ野菜は育たない。
●鶏ふん、牛ふんなどのチッソ成分が多い堆肥をしっかり発酵させてから畑に入れる。
●連作障害は仕方がない(マメ科は除く)
●ミミズがいるのは良い畑?!
●ムシが付くのは安全な野菜?!
どれも私にとっては違うような気がしてなりません。
まもなく梅雨明けです。この時期まだ一年目畑では野菜を作りません。徹底的に土を創ります。
具体的には竹、もみ殻、雑草などの炭素資材を大量にいれます。
やることは明確になってきました。気合いを入れないと…。